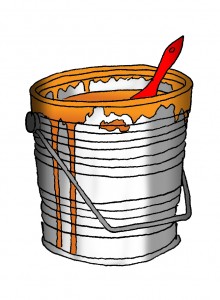虹描き人アルコ~消えた虹ペン~ 第1話
第1話 7色のペンキ
文・写真/こぐれ京 イラスト/なか山浩太朗
砂の白。そして、海の青。途方もない青。その端から天へと昇る、細い、薄い、虹。
その根を目指して、アルコはひたすら進んでいた。
ビーチに踏み込んでから、最初の20歩くらいは走った。
でもすぐに胸がゼイゼイ言って、足がグラグラして、たまらなくなって止まった。
歩けば歩くほど、体から力が抜けていく。
これが疲れというものだと、もちろん知ってはいたけれど――
感じるのは、初めてだった。
当然のように体に染み渡っていく、拒みようのない感覚。
今となっては、どうして今まで何をしても疲れなかったのか、不思議なくらいだ。
でも、きっとそれが虹描きというものだったんだろう。
そして、虹ペンをなくしてしまった今、アルコは虹描きとはまったく別の、何かになってしまったのだ。
それは途方もなく、心細いことだった。
早く虹ペンを取り戻したい。あの虹のふもとにはきっとまだ、あの虹ペンを使って
虹を描いた誰かがいるに違いない。
そう思って見上げると――
もう、空は青一色だった。
虹は消えてしまっていた。
よくあることだ。虹って、追いかけると、夢みたいに消えるんだよ。
知ってはいても、うろたえた。
虹の根があると思っていたビーチの端には、今にも崩れそうな建物があった。
砂浜から短い階段を上がると、いくつか席があるせまいテラスと、店の入り口がある。
古い家を解体して、部品を寄せ集めて作ったような、ペンキのはげた小さなカフェ。
部屋の中には、果物や枯れ枝がいくらか放り込んであるガラスケースや、
テーブル席が2、3見える。
「ねえ、ねえ、あの」
不意に声をかけられ、アルコは驚いて振り向いた。
「虹描きさんですよね。嬉しいな、僕、会ったの初めてです。やっぱり、普通の人とは違う感じなんだなー」
いつのまにか、アルコのすぐそばに。おびえたような疲れたような、
そういう訳ですべてを投げ出してしまったような、乾いた笑顔の青年が立っていた。
「ひょっとして、このあたりから、虹、出してくれるんですか」
期待を込めた目で見つめられ、アルコは戸惑う。
こういうことは、今までも時々あった。虹描きのことが見える人、
認識できる人というのは、実はかなりの数いる。
でもアルコはデビュー前の、修行中の虹描きなのだ。
まだ、こういう視線には慣れていない。どんな顔をしたらいいのか、困ってしまう。
しかも今は、その「修行中の虹描き」ですらなくなってしまったみたいなのだから。
「いや……今あの、ペンがなくて、虹、描けないんです」
「えー、そっか」
虹を描くには、虹のペンがいる。
それを説明しなくても知っているのか、それとも察しが早いのか、青年は
「ペン、どうしたんですか。壊れちゃったとか?」
と、心配し始めた。
アルコは、我ながら情けなくなってきた。
ペンをなくして途方に暮れる虹描き、それが今のぼくだ。本当に、自分にガッカリだ。
だいたい、マエストロがこんなことを知ったら、どう言うだろう?
「さっきの虹を描いた人、見ませんでしたか。ぼくのペンを拾ったのかもしれないんです」
「エー、見てないけどな。もしよかったら、うち、ペンキならあるけど……使います?」
「……ペンキですか」
ペンキで虹を描くなんて、考えたこともなかった。
「ペンキじゃ無理だと思います」
「ハハハ、やっぱダメだよね、ペンキじゃね」
青年は諦め顔で笑った。
そこへ、犬の鳴き声が聞こえてきた。
「シロ! シロ!」
青年が呼びかけると、白くてモジャモジャの犬が店の裏から走ってきた。
大きくなりすぎた小型犬。そんなキレの悪い容姿。
アルコは自分の目を疑った。あまりにも見慣れた犬だったから。
その犬は、くわえてきた物を地面に置くと、
「ワオン!」
と鳴いて、青年に飛びついた。
「お、なんだ、ペンキの話をしてたから刷毛、持ってきてくれたのか。かしこいなーシロは」
青年も、草の上にひざをつき、肩まである髪を振り乱して犬にジャレついた。アルコは呆然と、それを眺める。
「マエストロ……?」
「え? シロって虹描きさんの犬? 三日前くらいからウロついてるんだけど」
「ぼくの師匠の……マエストロ……だと思う」
大きさも、体つきも顔つきも、どう見てもマエストロだった。
でもどうして四つ足で歩いてるんだ。
「さっきの虹、マエストロが描いたの?」
その割には、細くてはかない虹だったけど。
「ワオン?」
どうして犬みたいに鳴いてるんだ。
いつも平気で2本足で歩いて、しゃべってるじゃないか。ペラペラと、いらないことまで……。
ハッハッハッハッ……。
嬉しそうな息を吐きながら、そのマエストロらしき犬は、刷毛をアルコの方へ押し出した。
「これって、ペンキで描いてみろって、シロが言ってるんじゃない?」
そう青年が言ったとき、アルコも、同じことを考えていた。
ペンキでもいい。虹を描くことができれば、きっと安心できるだろう。
でも、もし描けないなら……?
「やってみる? ペンキ取ってくるよ」
青年は、もう店の裏へと歩き出していた。
青年は、トシと名乗った。
トシさんに借りた刷毛にペンキをつけ、アルコは持ち上げてみる。
空へ。
派手な黄色の後ろに、底抜けな青がある。
刷毛をシュッと振ってみる。
ただ黄色の飛沫が、白い砂に点をならべた。
空中に、ペンキで何か描けるわけがない。そりゃ、そうだ。
分かっていても、動揺してしまう。
「ええ……と」
アルコが黄色い点を見つめていると、
「フフン」
と、犬が鼻を鳴らした。
やっぱりこの犬はマエストロだと、アルコは改めて確信した。
師匠のくせに、あまり暖かみのない笑い方をするのは、いつものことだ。
「あ、じゃあ、この壁あたりに」
トシさんは板壁に駆け寄って、腕を振って示した。
古びた柵をどこからか拾ってきて、門の代わりに立てたものだろう。
ペンキがはがれてボコボコした表面は、いかにも塗ってほしそうに待っている。
塗りたくりたい。
7色で、力いっぱい!
「いいんですか」
「いいですっていうか、頼みます。入り口のわきに虹なんてサイコーじゃない。
しかもそれ、本物の虹描きさんが描いたなんてさあ」
本物の、という部分にアルコはまた少し、うろたえた。
でもアルコは、この仕事を、もう他の誰にも渡したくなかった。
ぼくが、やりたい。
虹を、描きたい。
とろけるような温度の風が、ゆるりゆるりと吹き過ぎていく。
乾いているわけでもなく、湿っているわけでもない。
防砂林の松の木と、のんきに伸び切っているヤシの木の影にかくれて作業をするなら、
今日は素敵な天気だ。
いや、この島ではきっと、明日も明後日もしあさっても一年後も十年後も、
きっと、こんな天気なんだろう。
ずっと、ずっと、素敵な天気が続くんだろう。
やさしい島にやってきたみたいだ。
そう、思えた。
門とも看板ともつかない板に、アルコは、はみ出しそうな虹を描いた。
本当に七色もペンキを持っていたトシさんは、なんて素敵な青年だろう。
虹のできばえには、とても満足したようだった。
「いやあ、さすが虹描きさんだね。どうもありがとう! ところでそろそろ、おなか、すきません?」
「え? ああ、いや、ぼくは……」
ギュギュー、と何かが鳴った。
アルコの腹だ。
「漫画みたいだなあ!」
と、そのタイミングに、トシさんが笑った。アルコは笑えなかった。
虹描きが空腹になる? そんなことが、あるんだろうか。やっぱり何かがおかしい!
いったいぼくは、何なんだろう?
またアルコは考え込んだ。それには構わず、トシさんは奥の調理台で腕をふるい出した。
ひき肉と目玉焼きが白いライスに乗っかったプレート。
耳に絶えず届く波の音が、塩味をちょっと足しているようだった。
とてもおいしかった。
おいしい。それも、初めてのことだった。
もちろん、フォークやナイフを使って、手と口を働かせて食べることも、初めてだ。
だけど、なぜか当たり前のように、アルコはその偉業を成し遂げた。
トシさんだって、まさか物を食べるのが初めてとは気がつかなかっただろう。
アルコは自分でも驚きすぎて、それに怖くて、トシさんにそれを説明できなかった。
だから、おいしいという気持ちだけを顔に表して、ほかの消化できない色々は、
とりあえず腹の中にしまいこんた。
師匠はといえば、相変わらずひと言も話さない。
ただ、「シロ」と書かれた皿のハンバーグに、夢中で食らいついている。
マエストロだって、こんなふうに物を食べることがあったっけ?
思い返してみても、そんな記憶はない。
それなのに、師匠はあまりにも当たり前に、嬉しそうに食事をしている。
床の上で、四つん這いで。
アルコは、自分の記憶の森に霧がかかっていくような、ドンヨリとした気分になった。
虹描き人アルコ~消えた虹ペン~とは?
世界各地に虹を描いて、旅している虹描き人アルコが
とある南の島で体験した不思議な物語。
書いた日: 2010年 11月 8日 カテゴリー 虹描き人アルコ ~消えた虹ペン~
タグ: ハンバーグ, ペンキ
コメントを書こう!
You need to login to post comments!

 曼荼羅WEB
曼荼羅WEB